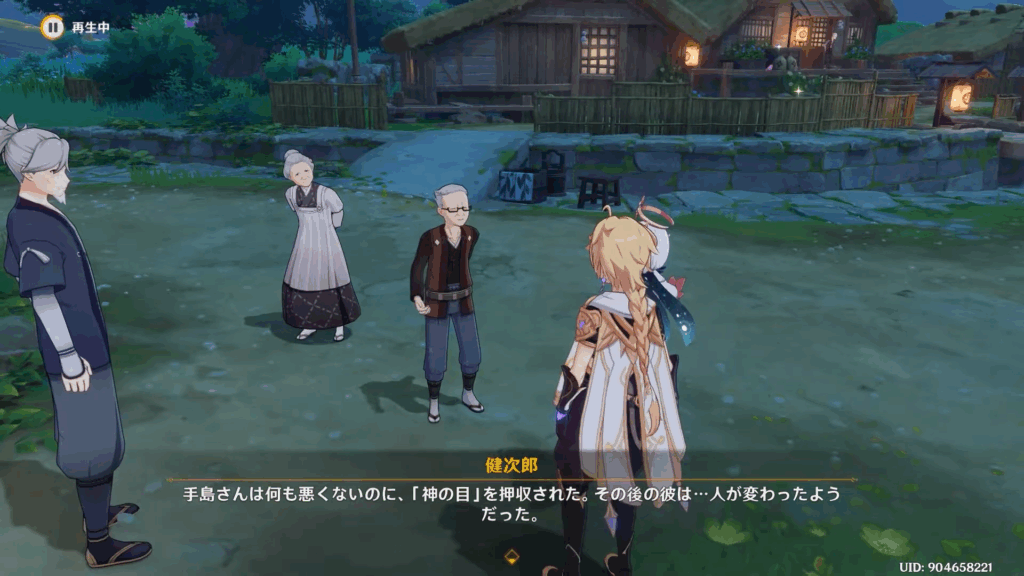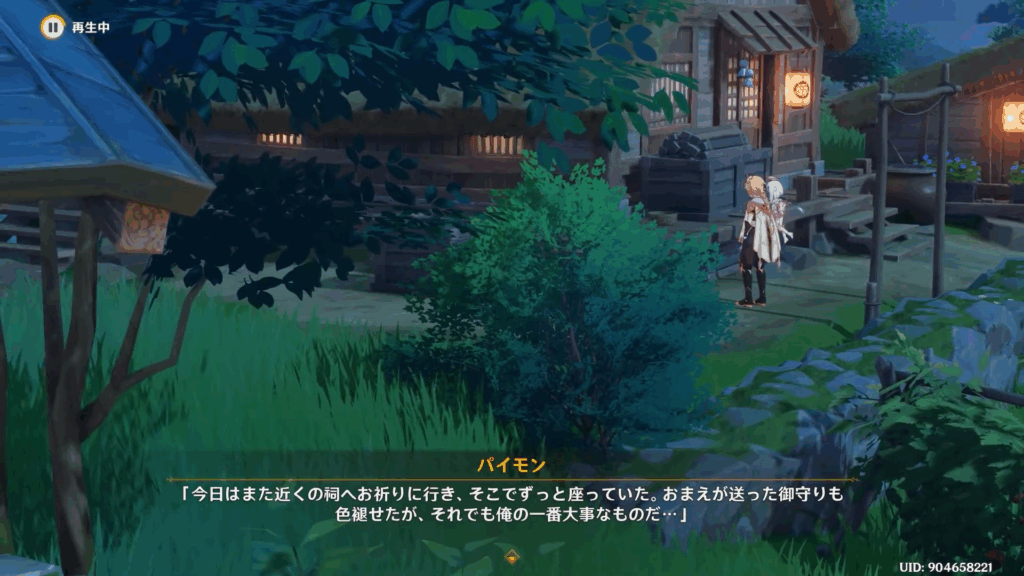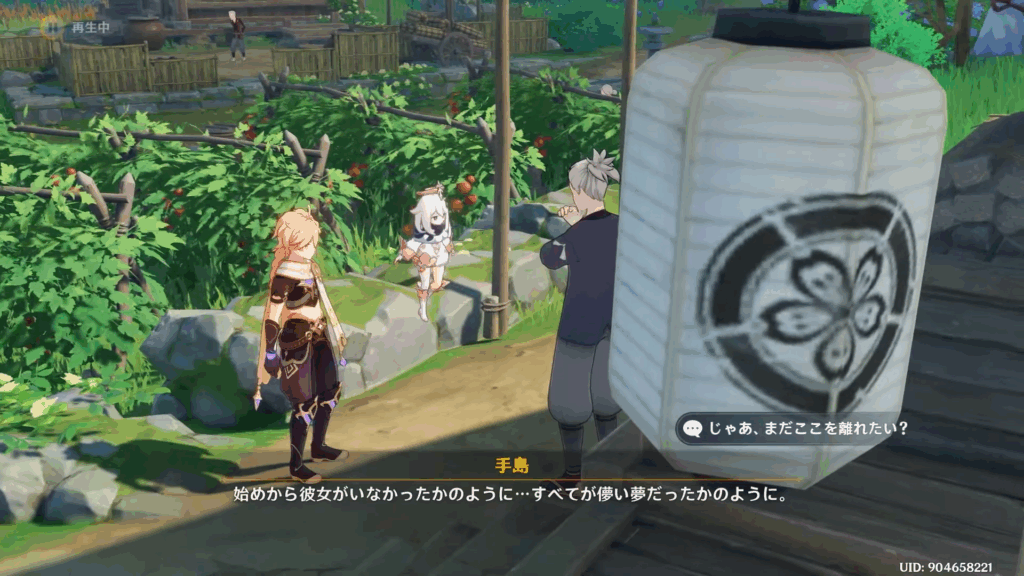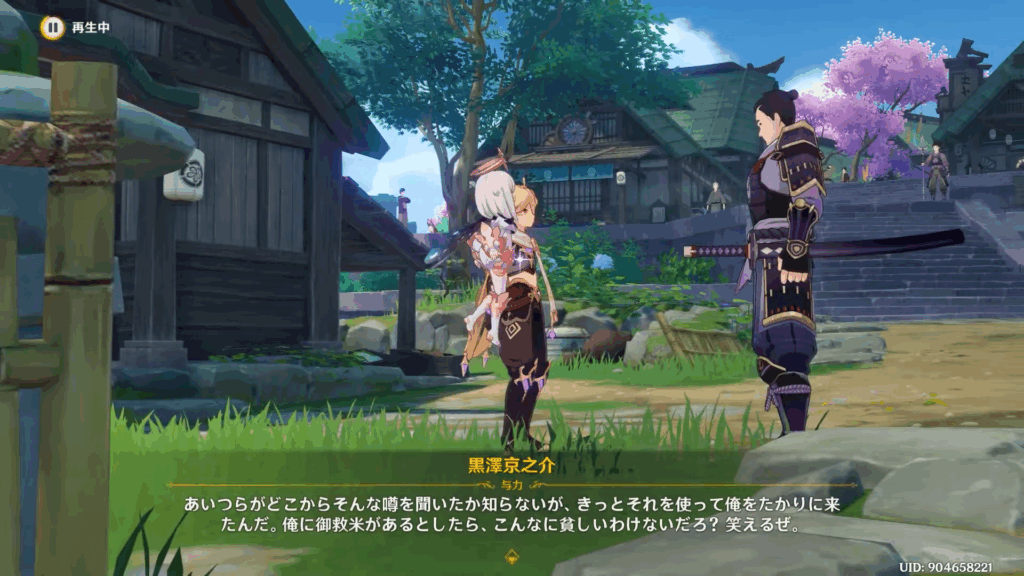第二章(稲妻編)第一幕「鳴神不動、恒常楽土」をスクショを交えつつ、振り返りたいと思います。
時系列的に出てきた内容に触れるだけなのでネタバレはないはずです。
最後に元動画も貼り付けてありますので、宜しければそちらもご覧ください。
神里綾華の頼みで、まずは一人目の村を守る武人に会いに行く。
「手島」という人は30年前からこの村にいるが、急にここを離れると言い出したとのこと。「神の目」を押収されてから人が変わったようだ。
手島に話を聞くと、彼はどうしてここに居続けているのか分からないという。30年前にどうしてここに来て、どうして30年もの間ここにいたのか、と。
「神の目」を奪われてから、たくさんのことを忘れてしまったようだ。彼が書いていた日記に何か手がかりが残っているかも知れない。
日記には日常のことが多く書いてあったが、気になる部分もあった。
日記に書いてあった、近くの祠に手がかりの御守りを見つけた。色も模様も女の子のもののようだ。
残っている手島の元素力を辿ると、そこには時間が経ちすぎて黄ばんでいる手紙が入った箱が埋めてあった。
手紙には、戦争で散り散りになったら紺田村で待っていて、という内容が書いてあった。紺田村はこの村の名前だ。
日記も、御守りも、手紙も手島のもののようだ。彼は確かに30年、誰かを待っていた。
神の目を奪われてから、手島が大切にしていた彼女に関することは全て消えてしまったのだ。それはすべてが儚い夢だったかのよう。
彼はこれかも待ち続けるが、本当に彼女に会えたとしても名前すら口にできなかったら、彼女は悲しく思うだろうか。
神の目を失ったら、願いと関係あるすべてが同時に失われてしまうのかも知れない。悲しみの理由を失うのはもっと悲しい。
次は目狩り令を執行していた武士の元へ。そこでは騒ぎが起きていた。
黒澤という幕府軍の武士で、この近くで御救米を配っている責任者のようだ。以前は黒澤に会えば御救米を分けてくれたのに急にくれなくなったという。それがないと飢え死にしてしまうとも。
黒澤に話を聞いてみるが、御救米なんて知らない、御救米があるとしたらこんなに貧しいわけない、の一点張りだ。彼も食べる物にありつけていないそう。
幕府軍が難癖をつけて黒澤の神の目を押収したとのこと。しかし、なぜ黒澤が目狩り令に不満を抱いていたのか、彼は覚えていない。
黒澤はさっき強盗に入られて、宝盗団を追っている途中に彼らに止められたらしい。宝盗団を懲らしめて、黒澤の家に御救米があったか聞いてみることに。
宝盗団を懲らしめて、話を聞くが、黒澤の家には何もなかったと言う。唯一、価値のありそうな箱を持ち出したが、まだ開けていない。
その場で開けてみるが、中には大量の借用書が。雑貨店の葵さんから借りたもののようで、かなりの金額のようだ。
一体、どういうことだろう?
話を聞くと、黒澤は定期的にここで大量の食料を購入していたようだ。しかも、彼自身のモラで。
しかし食料の値段が上がり、彼の俸禄では足りなくなったのか、借用書でモラを借りながら同じ量の食料を交換していた。
どうやら黒澤は人々の気持ちを大事に思い、借金をしてでも以前と同じ量の食料を換えてきたようだ。
彼がなぜお金を払って御救米を買ったのか、どうしてそれを公表しなかったのか、葵も聞かされていなかった。
黒澤は父から譲り受けた刀を年中身につけており、どんな高値でも売らないと言ったようだ。そこに探している答えがあるかもしれない。
黒澤の元に戻り、聞いてきたことを伝えるが、彼は何も思い出せなかった。
刀は黒澤の父親が亡くなる直前に彼に渡したもので、よく見ると刀の柄に何か刻んである。
そこには「仁義」という文字が。
黒澤は借金をしてでも他人の幸せを願う、それが自分にとっての最大の願いだったのだろう、と言った。
天領奉行に神の目を奪われ、助けていた人々からも理解されない。善人にも、悪人にもなれない。
彼もまた、神の目を奪われたかわいそうな人なのだった。